卒園アルバムのつくりかた
BLOG Archive
- 卒園アルバムTOP
- 卒園アルバムのつくりかた
- 卒園アルバムの写真トラブルベスト5!その問題と悩みを解決します
2025.2.2
卒園アルバムの写真トラブルベスト5!その問題と悩みを解決します

初めて卒園アルバムの制作を任されると、誰もが写真に関する悩みを抱えるものです。
写真の選び方や保管方法、撮影時の設定など…。
私も過去13年間、卒園アルバム専門メーカーとして数多くのご相談を受けてきました。
スマートフォンのカメラ性能が飛躍的に向上した今では、誰もが気軽に写真を撮れるようになりました。
その一方で、写真の量が膨大になり、選定や整理に頭を悩ませる方も増えています。
また「スマホの写真で印刷は大丈夫?」「カメラマンが撮影した写真は使えるの?」など、写真の品質に関する不安の声も多くお聞きします。
今回は、卒園アルバム制作でよく直面する写真の問題トップ5と、その解決方法についてご紹介します。
5つの問題は次の通りです。
- 1.膨大な量の写真からの選定
- 2.低品質写真への対処法
- 3.画質を保った写真の保管・共有
- 4.理想の撮影カメラとテクニック
- 5.写真枚数によるレイアウトの工夫
これから制作を始める方も、すでに悩みを抱えている方も、この記事がお役に立てば幸いです。
- 1000枚以上ある写真から選ぶのが大変…
- 写真の画質が荒くて印刷に不安
- LINEで写真を共有したら画質が下がってしまった
- スマホで撮影して大丈夫?高いカメラが必要?
- 写真が多すぎる/少なすぎてレイアウトに困っている
- 子どもの写真の枚数に差が出てしまいそう
目次
1.膨大な量の写真からの選定

春の遠足から始まり、運動会、発表会と行事写真が増えていく中で、特に運動会などの大きな行事では1000枚を超える写真が集まることも珍しくありません。
これだけの写真から、限られたアルバムのページ数に収めるための選定作業は、想像以上に大変な作業となります。
でも、コツを押さえることで効率的に進められます。
写真選びの負担を減らしながら素敵なアルバムを作り上げていきましょう。
作業を効率的に進めるコツ
写真選びは思った以上に時間がかかり、一人で黙々と作業を続けると心が折れてしまうことがあります。
そうなると「もういいや、適当に選んでしまおう」という気持ちになってしまいがち。
せっかくの思い出のアルバムですから、そうならないための対策が必要です。
複数人での作業分担方法
写真選びは必ず複数人で行うことをおすすめします。例えば、3人のチームであれば次のように分担すると効率的です。
- 1人目:まずは園児の表情が良く写っているものを選ぶ
- 2人目:1人目が選んだ中から、行事の雰囲気が伝わる写真を選ぶ
- 3人目:最終チェックと園児の写真枚数バランスの確認
このように役割分担をすることで、一人あたりの負担を減らせるだけでなく、それぞれの視点で写真を吟味できる利点があります。
写真選定の優先順位
まずは「絶対に使いたい写真」を探すところから始めましょう。具体的には、
- 1.園児全員が写っている集合写真
- 2.行事の見せ場となるシーン
- 3.子どもたちの生き生きとした表情が写っているもの
これらの写真を先に確保することで、その後の選定作業がスムーズになります。
また、写真を見る時は「この写真は何を伝えたいのか」という視点を持つことが大切です。
単に「きれいに撮れている」だけの写真は意外と思い出に残らないものです。
公平性を意識した選び方
「全ての園児を同じ枚数で掲載したい」という思いは自然なことですが、あまりにも神経質になりすぎると、かえって不自然なアルバムになってしまう可能性があります。
写真の枚数に多少の差が出ることは避けられません。
むしろ大切なのは、一人一人の園児の「いい表情」「印象的な瞬間」が最低1枚は入っているかどうかです。
この点については、年度初めの保護者会で「掲載枚数に差が出る可能性がある」ことを説明し、ご理解をいただくことをおすすめします。
選定作業の環境づくり
選定に使用する機材やソフト・アプリによって作業効率は大幅に異なってきます。
スマホとパソコンの使い分け

あくまでもパソコン所有が前提ですが、写真選びはスマートフォンよりもパソコンでの作業をおすすめします。
パソコンなら複数の写真を同時に表示して比較できるため、より効率的に選定作業が進められます。
特に、似たような写真が複数ある場合は、パソコンの大きな画面で見比べることで、より良い1枚を選びやすくなります。
ただし、移動中やちょっとした空き時間に写真を見る場合は、スマートフォンの方が便利です。
まずはスマートフォンで「候補となる写真」をピックアップし最終選考はパソコンで行うという使い分けがおすすめです。
グルーピング機能の活用法
パソコンが無くスマホのみで選定を行う場合グルーピング機能を活用して効率化すると良いでしょう。
最近のスマートフォンやクラウドサービスには、AIによる顔認識機能が搭載されているものが増えています。
この機能を使うと、特定の園児が写っている写真を自動的に見つけることができ、選定作業の効率が大幅に向上します。
主なサービスとその特徴は次の通りです。(2025年2月現在)
最も普及している写真管理サービス。顔認識の精度が高く、一度タグ付けした顔は自動的に分類されていきます。無料で15GBまで使用可能で、写真のバックアップ先としても優秀です。特に「思い出」機能では、1年前の同じ園児の写真を自動的に表示してくれるため、成長記録としても活用できます。
iPhoneユーザーなら最適な選択肢です。「人物」アルバムで自動的に顔がグルーピングされ、さらに時系列で写真を確認できる「メモリー」機能も便利です。iCloudの5GBまでは無料で使えます。
Amazonプライム会員なら無料で無制限に写真を保存できるのが魅力です。顔認識機能も搭載されており、複数人での共有も簡単。ただし、無料プランでは広告が表示されます。
専用アプリながら、子どもの写真に特化した機能が充実しています。顔認識に加えて、アルバムを見た人の「リアクション」も残せるため、祖父母との写真共有にも活用できます。無料で使用可能です。
ただし、これらのAI機能にも限界があることを知っておく必要があります。例えば、
- 帽子やマスクをしている場合の認識率が下がる
- 横顔や後ろ姿は認識されにくい
- 集合写真での顔認識は不完全な場合がある
- 屋外での逆光写真は認識されづらい
- 突然サービスが終了する可能性も否定できない
そのため、グルーピング機能は「下準備」として活用し、最終的には目視での確認が必要です。
また、これらのサービスを使用する際は、園児の写真をクラウドにアップロードすることになるため、園の方針や保護者の同意を得ることも忘れずに確認しましょう。
プライバシーに配慮しながら便利な機能を活用することが大切です。
写真整理のテクニック
大量の写真を効率的に選ぶには、整理方法も重要です。
以下のような手順で整理していくと作業がスムーズになります。
まずは行事ごとにフォルダを分け、その中をさらに「集合写真」「個人写真」「スナップ写真」のように分類します。
そして各分類の中で★印などを付けて、候補となる写真を明確にしていきます。
このような地道な整理作業が後々の効率的な選定につながります。

特に気を付けたいのは、撮影者を絞ることです。
同じ場面を複数のカメラで撮影すると確かにベストショットを逃さない利点はありますが、その分選定作業が煩雑になります。
むしろ撮影者を決めて、その人が確実にシャッターチャンスを逃さないようにする方が結果的に効率的な作業につながります。
2.低品質写真への対処法

スマートフォンのカメラ性能が飛躍的に向上した現代でも、行事の撮影では暗かったり、ブレてしまったりする写真は避けられません。
特に室内での発表会や、動きの速い運動会のシーンでは、思うように写真が撮れないことも多いものです。
でも、写真の見極め方と簡単な補正方法を知っておくことで、多くの写真を活かすことができます。
デジタルズームと光学式ズーム
スマホ撮影で最も重要なことについて触れたいと思います。
画面を「ピンチイン・ピンチアウト」でズームし撮影する写真は「画質劣化」を引き起こします。
これはモニターに映し出されてる画像の一部を「拡大切り取り」しているため、元画像の「ピクセル」が拡大して「ぼやけ」たり「カクカク」した画像になってしまうのです。
標準以外の「レンズ」が搭載されてるスマホでの「光学式ズーム」の使用であれば問題ありません。(それでも標準よりは画質低下の傾向にあります)
このことから、スマホ撮影は「ズームしない」を基本とし、可能な範囲で自分が近づいてシャッターを切ることをお勧めします。
スマホ撮影に関連するブログ記事をご案内します。
写真の品質を見極めるポイント
印刷に適した解像度とは

印刷用の写真で最も重要なのは「解像度」です。
スマートフォンの画面では綺麗に見える写真でも、印刷するとモザイクのように荒く見えてしまうことがあります。
一般的なアルバムでは、300dpi以上の解像度が推奨されます。
例えばL判サイズ(89×127mm)で印刷する場合、1050×1500ピクセル程度の画像サイズが必要です。
最近のスマートフォンであれば、通常撮影でもこの条件は十分にクリアできます。
ただし、トリミング(画像の切り抜き)を行う場合は要注意です。例えば画像の4分の1にトリミングすると、解像度も4分の1になってしまいます。
大きくトリミングする予定がある場合はできるだけ高解像度で撮影しておきましょう。
こちらのブログでは、さらに詳しく「解像度」について解説しています。
暗い写真の見極め方
暗い写真には大きく分けて2種類あります。
1. 全体的に暗いが細部は見える写真
→補正で十分に改善できます
2. 真っ暗で細部が判別できない写真
→補正での改善は困難です
特に気を付けたいのは「人物の表情」です。
表情が判別できる写真であれば多少暗くても補正で活かせる可能性が高いと考えてよいでしょう。
補正で改善できる範囲
補正ツールで改善できる主な項目は
- 明るさの調整(露出補正)
- コントラストの調整
- 色味の調整
- ノイズ(ざらつき)の軽減
一方で、以下のような問題は補正での改善が難しいため、写真選びの段階で避けることをおすすめします。
- ピンボケ
- 激しいブレ
- 完全な白飛びや黒つぶれ
写真補正の基本テクニック
おすすめの補正アプリ

手軽に使える写真補正アプリをいくつかご紹介します。
Googleが提供する高機能な補正アプリです。直感的な操作で明るさやコントラストを調整できます。「HDR」機能を使うと、暗い写真でも自然な明るさに補正できます。
プロも使用する本格的な補正アプリです。「自動」補正機能が優秀で、初心者でも簡単に写真を改善できます。無料版でも十分な機能が使えます。
写真補正の定番ソフトの簡易版です。「ワンタッチ補正」が充実しており、複数の写真を同じ設定で一括補正できる機能も便利です。
写真補正の大切さをテーマにしたブログも併せてご覧ください。
また、実際に色々な補正ツールを使用し「ビフォーアフター」を画像で紹介した姉妹サイトのブログがございます。
業者補正のメリット

写真の補正に不安がある場合は、アルバム制作業者に依頼するのも一つの方法です。
プロの技術で写真を最適化してくれるため印刷時の仕上がりが格段に良くなります。
ただし、業者によって補正サービスの有無や料金が異なりますので、事前に確認が必要です。
また、補正を依頼する場合でも、あまりにも品質の悪い写真は避け、ある程度見える状態の写真を選んでおくことが大切です。
ちなみにキッズドン!の「おまかせコース」には、全ての写真に補正を行うサービスが無料で含まれています。
思い出重視の写真選び
写真の品質にこだわるのは大切ですが、それ以上に大切なのは「その写真に写っている場面の価値」です。
例えば、少し暗くても園児の感動的な表情が写っている写真や、ブレていても行事の雰囲気が伝わる写真は十分にアルバムに使える価値があります。
逆に、技術的には完璧でも表情が硬かったり、posed(ポーズを決めた)過ぎる写真は、思い出としての価値が低いかもしれません。
写真選びの際は「技術的な品質」と「思い出としての価値」のバランスを考えながら総合的に判断していくことをおすすめします。
「ダメダメ写真でも貴重な思い出」をテーマにしたブログもよろしければご覧ください。
3.画質を保った写真の保管・共有

卒園アルバム制作では、大量の写真をアルバム委員同士で共有する必要があります。
「LINEで送ったら画質が荒くなった」「写真を保存する場所がいっぱいになった」など、写真の共有と保管に関するトラブルは意外と多いものです。
快適に作業を進めるために、適切な方法を知っておきましょう。
写真共有時の注意点
とくに「LINEアルバム」の使用に十分ご注意ください。
LINEでの写真共有のコツ

LINEは手軽で便利な反面、写真の画質が大幅に低下してしまう難点があります。
特に「LINEアルバム」での共有は要注意です。アルバムに保存された写真は印刷には適さないほど画質が落ちてしまいます。
ただし、LINEでも画質を保ったまま写真を送る方法があります。
- トーク画面で写真を送る際、「写真」アイコンではなく「ファイル」から送信
- 写真選択時に「元の画質で送信」を選択
- 一度に送れる枚数は少なくなりますが、画質は保たれます
SNSでの画質劣化を防ぐ方法
InstagramやFacebookなどのSNSも、写真の共有手段としてよく使われます。
しかし、これらのプラットフォームも自動的に写真を圧縮してしまいます。
SNSでの共有が必要な場合は、以下の点に注意しましょう。
- 投稿前に画質設定を最高品質に変更する
- 投稿後の写真はダウンロードして使用しない
- 原本は別途保管しておく
こちらのブログもぜひご参照ください。
大容量ファイル転送サービスの選び方
大量の写真を高画質のまま共有するには、専用の転送サービスの利用がおすすめです。
これらの転送サービスは操作方法も簡易的あり安心して使用することができます。
写真の保管方法
クラウドサービスの活用

写真の保管には、クラウドサービスの活用が効果的です。主なサービスとその特徴をご紹介します。
- 15GBまで無料
- 写真の自動バックアップ
- 共有設定が柔軟
- 5GBまで無料
- Windowsとの相性が良好
- 自動同期機能あり
- 5GBまで無料
- Apple製品との連携が優秀
- 写真の自動整理機能
バックアップの重要性
どんなに気を付けていても、機器の故障やアクシデントは起こりえます。
大切な卒園アルバムの写真は必ず複数の場所にバックアップを取っておきましょう。おすすめのバックアップ方法として、
- スマートフォン本体
- パソコンのハードディスク
- クラウドストレージ
- 外付けハードディスクやUSBメモリ
少なくとも2か所以上に保存しておくことで、万が一の事態に備えることができます。
4.理想の撮影カメラとテクニック
園児の大切な思い出を残すカメラ選び。
「高価な一眼レフじゃないと駄目なの?」「スマホのカメラでは不安...」
といった声をよくお聞きします。実際の現場で数多くの写真を見てきた経験から、それぞれのカメラの特徴と、シーンに応じた使い分けについてご紹介します。
各カメラの特徴と使い分け
今やスマートフォンのカメラ性能は飛躍的に向上し、日常のスナップ撮影には十分な画質を誇ります。
一方で、運動会や発表会といった特別な行事では、一眼レフカメラやコンパクトデジカメならではの良さも健在です。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
スマホカメラの限界と活用法

スマートフォンカメラは手軽さが最大の魅力です。
しかし以下のような制約があります。
- デジタルズーム撮影時の画質低下が著しい
- 暗い場所での撮影が苦手
- 動きのある被写体のブレが出やすい
これらの弱点を踏まえた上で、以下のような場面での活用がおすすめです。
- 園庭での遊び場面
- お散歩や制作活動
- 給食やおやつタイム
- 近距離での表情撮影
写真を撮る際は以下の点に気をつけると、より良い写真が撮れます。
- グリッド線を表示して構図を整える
- HDRモードをオンにして明暗差の大きいシーンに対応
- 連写機能を使って決定的瞬間を逃さない
- タップして露出を合わせる
一眼レフカメラのメリット

運動会や発表会といった特別な行事では、一眼レフカメラの実力が発揮されます。
- 望遠撮影でも高画質を維持
- 暗い場所でも明るく撮影可能
- 動きのある被写体も鮮明に撮影
- 背景のボケを活かした印象的な写真に
一眼レフは決して難しい機械ではありません。エントリーモデル(Canon EOS KissやNikon D3000シリーズなど)であっても、オートモードで十分な写真が撮影できます。
大切なのはレンズの選択です。特に室内行事では明るいレンズ(F値2.8以下)があると格段に写真の質が向上します。
また最近はレンタルサービスも活況ですのでこれを利用するのも一案です。
一眼レフの撮影テクニックについては、後述いたします。
コンパクトデジカメの活用

一眼レフとスマートフォンの中間的な存在として、コンパクトデジカメも検討に値します。
- 望遠撮影に強い機種が多い
- 一眼レフほどの大きさ・重さがない
- バリアングル液晶で高い位置からの撮影も容易
- Wi-Fi機能で即座にスマホへ転送可能
特に光学ズーム10倍以上の機種であれば運動会などでも十分な写真が撮影できます。
園の先生向けに書いた「カメラ機材の選び方」の記事がございます。
一眼レフの撮影設定とテクニック

せっかく一眼レフを使用するのであれば、その性能を最大限に活かした撮影がしたいものです。
行事によって適切な設定は異なりますが基本的な考え方をおさえておくと、より良い写真が撮影できます。
運動会でのカメラ設定用

運動会では動きのある被写体を確実に捉えることが重要です。
「シャッタースピード優先(Tvモード)」での撮影をおすすめします。
- かけっこや競技の撮影 → 1/500秒以上
- 玉入れやダンス → 1/250秒程度
- 入場行進や整列 → 1/125秒程度
ただし、晴天の日中であれば1/1000秒でも明るく撮影できますが、曇天や夕方は上記の速いシャッタースピードでは暗くなりすぎる場合があります。その場合はISO感度を上げて対応します。
最近の一眼レフはISO3200程度まで、それほどノイズ(ざらつき)が気にならない機種も多いため積極的に活用しましょう。
発表会や室内行事での設定

室内行事では背景をぼかして主役を引き立てる「絞り優先(Avモード)」がおすすめです。
- 個人の発表シーン → F2.8以下(可能であれば)
- グループでの発表 → F4.0前後
- 全体での合唱等 → F5.6以上
発表会では舞台照明が暗いことも多く、シャッタースピードが遅くなりがちです。
1/60秒を下回るとブレの原因となるため以下の対策を行います。
- 明るいレンズの使用(F2.8以下が理想)
- 三脚や一脚の活用
- 手ブレ補正機能をオンに
- 連写モードで複数枚撮影
「絞り値F2.8以下のレンズがおすすめ」という言葉を先ほどから列記していますが、この「F値」とは一体何なのでしょうか?
簡単に言うと、F値は「レンズに入ってくる光の量」を示す数値です。
F値が小さいほど多くの光を取り入れることができ暗い場所でも明るい写真が撮影できます。たとえば、
- F2.8は「明るいレンズ」
- F4.0は「やや明るいレンズ」
- F5.6は「標準的な明るさのレンズ」
と解釈されると良いでしょう。
スマートフォンのカメラは一般的にF2.0前後ですが、レンズが小さいため、一眼レフのF2.8とは光の取り込み方が異なります。
また、F値が小さいレンズには「背景をぼかす」効果もあります。
発表会で園児を撮影する時F2.8のレンズを使うと、園児の姿がくっきりと写り、後ろの背景は優しくぼやけた印象的な写真になります。
ただし、高価なレンズを購入する必要はありません。最近では、カメラ量販店やネットでレンズのレンタルサービスも充実しています。
発表会や運動会など、特別な行事の時だけレンタルするのもおすすめです。
ピント合わせのコツ

一眼レフでの失敗の多くは、ピントが合っていないことが原因です。以下の点に留意されると良いでしょう。
- AFモードは動きものはAIサーボ(ニコンはAF-C)
- 静物はワンショットAF(ニコンはAF-S)
- Fポイントは中央付近を使用
- マニュアルフォーカスでの撮影は避ける
光の扱い方とストロボ活用

室内での撮影で重要となるのが「光」のコントロールです。
- ストロボは直接ではなく天井にバウンスさせる
- 会場の照明を意識して露出補正を活用
- 逆光時はストロボで人物を明るく
- 窓際での撮影は露出補正を+側に
- 蛍光灯下ではホワイトバランスを調整
カメラマンの撮影をご覧になったことがあるでしょうか?
カメラの上に付属した大きめのストロボの光源は「真正面」ではなく「斜め上」を向いてることが多いことに気づきます。
これは「光源」を天井に発し、その跳ね返りで被写体全体を上から照らす手法=バウンス手法を使用しているからです。
被写体に「真正面」から光をぶつけると、陰影がなくなり「のっぺりとした不自然」な写りになるというご経験があると思います。
プロの撮影か素人の撮影か…を分ける決定的なストロボ発行方法ですので、ぜひお試しください。
ストロボはレンタルでも調達できます。
撮影前の準備と心構え
本番での失敗を防ぐため、以下の準備を行っておくと安心です。
- バッテリーの充電(予備も用意)
- メモリーカードの容量確保
- レンズの清掃
- 似た環境での試し撮り
- カメラの設定値を控えておく
- 撮影ポジションの確認
- 他の保護者の視界を妨げない配慮
特に発表会では、事前のリハーサルに参加させていただき、本番と同じ照明条件で試し撮りができると理想的です。
光の具合や、どの場面でどの設定が適しているか把握することができます。
このように一眼レフには多くの設定項目がありますが、基本的な考え方さえ押さえておけば、それほど難しくはありません。素晴らしい思い出の1枚を残すため、ぜひチャレンジしてみてください。
5.写真枚数によるレイアウトの工夫
「写真が少なくて寂しい...」「たくさんの写真を入れたいけどごちゃごちゃしそう...」。
写真の枚数によってレイアウトの悩みは尽きません。
でも、むしろ写真が少ないことはチャンスです。
シンプルで印象的なアルバム作りができます。
一方で写真が多い場合も、整理の仕方次第やアイデアで見やすいページとちょっとしたエンターテイメントに仕上げることができます。
それぞれの状況に応じたレイアウトの工夫をご紹介します。
写真が少ない場合の対処法
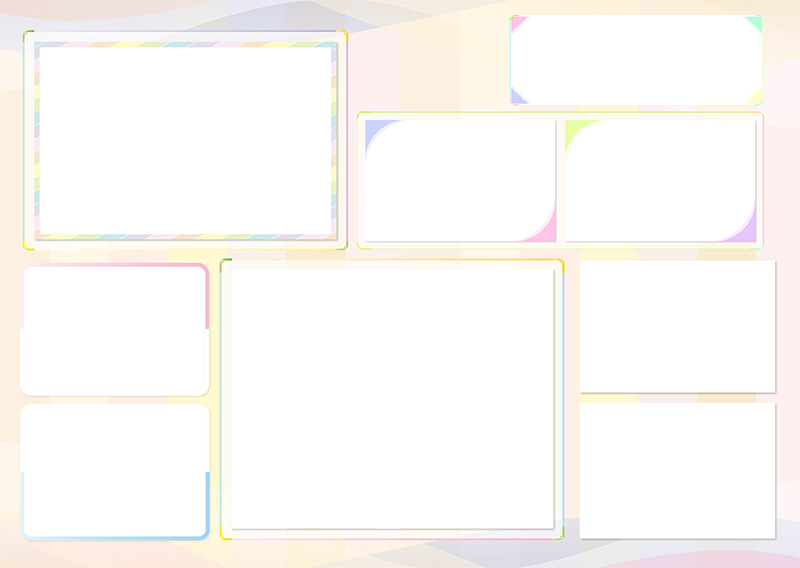
写真が少ない場合、「物足りない」と感じるかもしれません。
しかし少ない写真だからこそできる効果的なレイアウトがあります。
シンプルな構成のメリット
写真が少ないページには、次のようなメリットがあります。
- 1枚1枚の写真の細部まで見える
- 余白が生まれ、写真が引き立つ
- 伝えたいメッセージが明確になる
- 記憶に残りやすい
- 閲覧時の視線の流れが自然
特に見開きで1〜2枚の大きな写真を配置すると、絶大なインパクトがありそのページの印象が強く残ります。
写真と写真の間に適度な余白を設けることで、むしろ高級感のあるデザインに仕上がるのです。
大きく見せる工夫
少ない写真を効果的に見せるテクニックをご紹介します。
- 背景色を写真の色調に合わせる
- 写真の輪郭に細いフレームを付ける
- タイトルや日付を控えめに配置
- 余白を均等に取る
- メッセージや説明文を添える
- 写真の配置は左上か中央に
特に背景選びは重要です。派手な背景は避けパステルカラーや淡い色合いを選ぶと、写真が自然と引き立ちます。
ページ構成の見直し
写真が全体的に少ない場合は、以下のような工夫も効果的です。
- 行事ごとのページ分けを見直す
- 似たテーマの行事を統合する
- 個人ページの比重を増やす
- 園の四季や日常風景のページを作る
- 先生からのメッセージページを充実させる
少数写真点数作成をテーマにしたブログがございます。
写真が多い場合の整理術
反対に写真が多すぎる場合は、取捨選択と整理が重要になります。
アルバム制作にかける予算が潤沢にあれば「ページ数増加」も可能でしょうが、すでに保護者会等で承認されてるページ数の変動は現実的ではないでしょう。
ここでは「いかにページ数を増やさず多量の写真をまとめるか」をテーマに見ていきましょう。
コラージュの活用方法
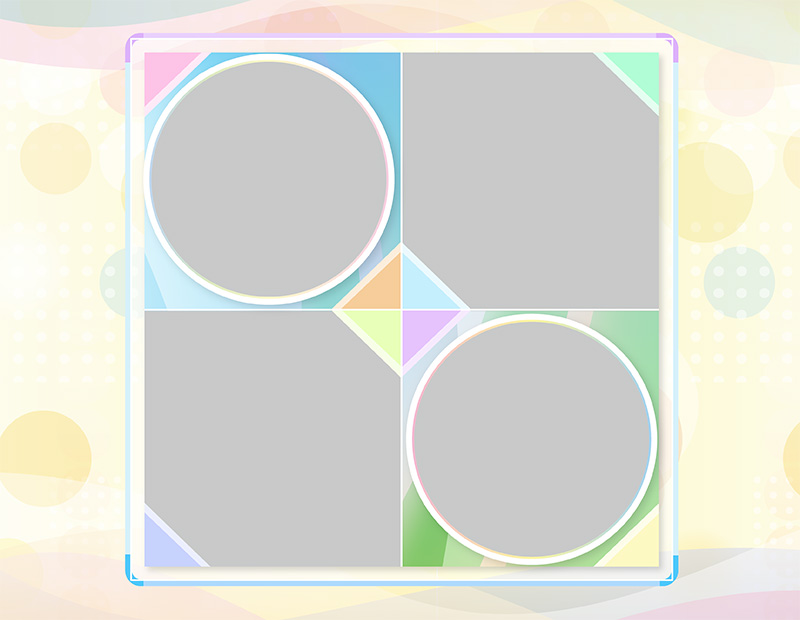
写真が多い場合、コラージュは効果的な手法です。
- メインとなる大きな写真を中心に
- 周辺に関連する小さな写真を配置
- 写真と写真の間隔を統一
- 色調の似た写真をグループ化
- 動きのある構図を心がける
- 重なりは控えめに
写真の優先順位付け
全ての写真を同じ大きさで扱うのではなく、以下のような基準で写真の大きさを変えるとメリハリのあるページになります。
- 集合写真は状況に応じて最大化
- 写る人数が多いほどサイズを大きめに
- 園児単体は可能であれば顔アップにして小さめに
- 遠景や環境写真は小さめに
- 行事の全体感が分かる写真を1点より抜いて大きめに
- 似たような写真はできる限り1点に集中させて後は削除
その行事は本当に載せるべきか?
例えば運動家や生活発表会などは保護者参加イベントのため、各家庭で撮影した写真や動画を既に所有してる可能性が高いと言えます。
このことから、保護者参加行事は極力掲載候補から外し、反対に「普段見れない園での様子」を中心に構成する方法が増加しています。
このような意向も保護者会などで事前承認を得ておくと、作成がスムーズに運ぶでしょう。
このような「何をアルバムに載せるか」をテーマにしたブログがございます。
デジタルデータの活用

卒園アルバムはなにも「ブックタイプのアルバム」で完結させる必要はありません。
アルバムに入りきらない写真は、デジタルデータとして別途提供する方法もあります。
- スライドショー動画の作成
- 写真集PDFの作成
- スピンオフアルバムの作成
- クラウドストレージでの共有
- 写真データをDVDやUSBメモリーに収録
- アプリやウェブサービスの活用
例えば、アルバムには厳選した写真を使用し、その他の写真はスライドショーにするという方法が効果的です。
BGMをつけることでより思い出深いコンテンツになります。
下の動画はキッズドン!の姉妹サイト「おもいでアルバム ザ・ムービー」のサンプルの一つになります。
スピンオフアルバムの作成は、格安で有名な「しまうまプリント」などのテンプレートを使用すれば、写真をどんどん入るだけですので、最低限の労力で完成させることができます。
このように、写真の枚数に関係なく、工夫次第で魅力的なアルバムを作ることができます。
こちらのブログもご参照ください。
おわりに
思い出をつづる卒園アルバム。写真の選び方やレイアウトの工夫で、そのクオリティは大きく変わってきます。
今回ご紹介した写真に扱いや撮影テクニック、またレイアウトの工夫については、あくまでも参考の一つです。
スマートフォンでも一眼レフでも、大切なのは「園児たちの笑顔や成長の瞬間」を捉えることです。
決して高価なカメラや複雑なレイアウトにこだわりすぎる必要はありません。
また、写真の枚数についても同様です。
多くても少なくても、一枚一枚に込められた思いが伝わるアルバムこそが、卒園生とそのご家族の心に残るはずです。
デジタルツールやテクニックは、あくまでもその思いを伝えるための手段。どうぞ楽しみながら制作を進めていってください。
私たちキッズドン!も、皆様の素敵な思い出作りのお手伝いができることを心より楽しみにしております。
今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それでは、また。

キッズドン! 代表 宗川 玲子(そうかわ れいこ)
(宣伝になります)
SNSで情報更新をお知らせします
ブログや、フリー素材の新作、ニュースなどの更新情報を、ツイッターとインスタグラムでお知らせしています。フォローしていただき最新情報をお受け取りください。















