はじめての卒園アルバム
BLOG Archive
- 卒園アルバムTOP
- はじめての卒園アルバム
- 卒園アルバムの写真撮影で押さえておきたいポイント5つ
2025.2.7
卒園アルバムの写真撮影で押さえておきたいポイント5つ

こんにちは、卒園アルバム制作メーカー キッズドン!の宗川 玲子(そうかわ れいこ)です。
今回は卒園アルバムに掲載する写真の撮影方法について、実践的なポイントをお伝えします。
プライベートでお子様を撮影する時とは異なり、卒園アルバム用の写真には特別な配慮が必要です。
画質設定から構図、撮影のタイミングまで、アルバム制作に携わるスタッフだからこそ知っている具体的なテクニックをご紹介します。
この記事を参考にお子様の大切な思い出をより美しく残していただければ幸いです。
- 卒園アルバム用の写真は、普段の写真とどう違うの?
- スマートフォンでも良い写真は撮れるの?
- 全身写真はどうすれば上手く撮れるの?
- どんな画質設定で撮ればいいの?
- プロのカメラマンは本当に必要?
- 写真を共有する時の注意点は?
目次
卒園アルバムに適した写真撮影の基礎知識
卒園アルバムに使用する写真と、普段撮影している写真では、その目的や求められる品質が大きく異なります。
プライベートでの撮影では、お子様の愛らしい表情や楽しそうな様子を切り取ることに重点を置きがちですが、卒園アルバム用の写真には、より広い用途に対応できる汎用性が求められます。
プライベート写真との違いを理解する
特に重要な違いとして以下が挙げられます。
- プライベート写真:気軽に撮影でき、すぐにSNSなどで共有できる
- 卒アル用写真:印刷や加工に耐えうる高画質が必須
記録写真と思い出写真の違い
卒園アルバムの写真は、単なる記念写真以上の役割を担っています。
レイアウトの一部として使用されたり、切り抜いて他の写真と組み合わせたりと、様々な用途に活用されます。
そのため、撮影時から「使用目的」を意識することが重要です。
高画質設定である程度拡大しても劣化しないクオリティを維持することや、同一シーンで個々の園児を撮影する際は、公平性を保つ目的で「ほぼ同じようなアングルと構図」に留意することなどが挙げられます。
1.全身写真を意識して撮影

卒園アルバムでは、お子様の全身写真が重要な素材となります。
特に切り抜きやレイアウトの素材として使用する際、全身のシルエットが自然で、動きのある写真が大切です。
ただし、この撮影が意外と難しく多くの保護者様が苦心されるポイントでもあります。
切り抜きに適した全身写真の特徴
全身写真の撮影では、つい表情を重視するあまり近づきすぎてしまいがちです。
しかし、アルバムのレイアウトでは、園児の全身シルエットを活かした構成も重要な要素となります。
代表的な撮影の課題として以下が挙げられます。
- 表情を追いかけるあまり上半身のみの構図になってしまう
- 動きのある瞬間を逃してしまう
- 体の一部が切れてしまう
切り抜きを綺麗に、そしてユーモラスに見せる鍵は「全身で切り抜く」ことにあります。
反対に下半身がカットされてる、伸ばした手の先がカットされてるような写真を無理やり切り抜いても、不自然さを招くだけとなってしまいます。
自然な動きのシルエット
理想的な全身写真は、お子様の自然な動きや表情が活き活きと表現されているものです。
特に園庭での遊び時間や行事の際は、無理にポーズを取らせるのではなく、自然な動きの中でシャッターを切ることを心がけましょう。
走っている姿や遊具で遊ぶ様子など、日常の一コマを切り取ることでより生き生きとした表情と動きのある写真が撮影できます。
切り抜き用写真撮影のコツ
次の点を意識して撮影されると良いでしょう。
- 1.縦画面構図で撮影
- 2.連写を使用
- 3.躊躇なくシャッターを切る
- 4.全身撮影を常に意識して
- 5.背景はシンプルにこしたことはない
特に最後の「5.背景はシンプルにこしたことはない」が重要です。
昨今「全自動でAIが切り抜きをするアプリ」が当たり前のように存在します。
このアプリやソフトが「苦手」とするシチュエーションに次のようなものがあります。
- 多くのオブジェクトが被写体の後方にある
- 被写体と背景が同一カラー
- 暗所
- 髪の毛や細かい造作の服や所持品
撮影の際、背景を意識しながら撮影するのは困難と思われますが、明る居場所でシンプルな背景のほうが、切り抜きの精度が格段に上がると覚えておいてください。
そしてもう一つが「連写を使用」です。
全身の自然な動きを捉えるために、カメラやスマートフォンの連写機能は強い味方となります。
特に動きの速いお子様の撮影では、一枚一枚のシャッターでは決定的な瞬間を逃してしまいがちです。連写機能を使用することで、その中から最適な一枚を選ぶことができます。
ちなみにCanonミラーレス一眼のR50は1秒間に15枚、iPhone15で1秒間に10枚の撮影が可能。
「とても良い写り、ピントもばっちり、ポージングも最高、でも目をつぶってる…」
と、ならない為にも連写をご活用ください。
撮影時の具体的なテクニック
お子様の全身を美しく収めるには、撮影者側にもいくつかの工夫が必要です。
繰り返しになりますが、注意点として以下を意識すると良いでしょう。
- 撮影位置は園児の目線の高さに合わせるる
- 背景はできるだけシンプルに
- 光の向きに注意(逆光を避ける
撮影の際は、余裕を持った構図で撮ることを心がけてください。
後からトリミングすることはできても、撮影時に切れてしまった部分を復元することはできません。
また、連写で撮影する場合は事前にスマートフォンやカメラの容量に余裕があることを確認しておくことも大切です。
全身写真は卒園アルバムの重要な素材となりますので、できるだけ多くの写真を撮影し、その中から最適なものを選べるようにしましょう。
2.アップはぐぐっと接近して

園児の愛らしい表情は、卒園アルバムを彩る重要な要素です。
アップ写真は原稿のアクセントとしても、思い出としても大切な役割を果たします。
しかし、ただ近づいて撮るだけでは印象的な一枚を残すことはできません。
適切な距離感とアプローチ方法を知ることで、より魅力的な表情写真を撮影することができます。
表情撮影の基本テクニック
接写撮影には、撮影者と被写体の信頼関係が不可欠です。
突然カメラを向けても自然な表情は撮れません。
まずはコミュニケーションを取りながら、リラックスした雰囲気を作ることが大切です。
特に次の点に注意を払うと良い結果を生み出します。
- 会話をしながら撮影する
- 身振り手振りをしながらシャッターを切る
- 無理に笑顔を作らせない
- 目線は自然な位置で
- お子様のペースを尊重する
- 構図はバストアップで
理想的な撮影距離を見つける
表情を撮影する際の適切な距離は、レンズの種類や撮影状況によって変わってきます。
一般的に、胸から上が収まる程度の距離が基本となります。
この距離であれば、自然な表情を引き出しやすく、かつ十分な解像度も確保できます。
また、この距離感は園児に圧迫感を与えることなく、コミュニケーションを取りながら撮影することができます。
自然な表情を引き出すテクニック
最高の笑顔は、自然な会話や遊びの中から生まれます。
なるべく「語りかけるように」「質問を投げかけ」「ジェスチャーを加えながら」シャッターを切っていきましょう。
ベストな撮影スタイルは「園児の気を引く担当者」と「撮影者」のペアで臨むことです。
気を引く担当者は「すぐにわかるクイズ」や「ちょっとしたマジック」、「最近園児の間でのトレンド情報」を用意しておき、園児を夢中にさせます。
撮影者はファインダー(スマホモニター)に集中できることから、より高品位な写真を収めることができます。
また、撮影者からのアプローチでなくとも、友達との会話や好きな遊びに興じている時など、リラックスした瞬間を狙うことで、より生き生きとした表情を捉えることができます。
接写撮影時の注意点
アップ写真の撮影では、技術的な面でもいくつか押さえておくべきポイントがあります。
特に以下の点に注意を払うことで、より質の高い写真を撮影することができます。
- ピント合わせを慎重に
- 手ブレに注意
- 適切な光量の確保
- デジタルズームの使用禁止
デジタルズームの使用は極力避け、物理的に近づいて撮影することをお勧めします。
デジタルズームを使用すると画質が劣化し、印刷した際に粗さが目立ってしまう可能性があります。
また、手ブレ防止のためしっかりとカメラを固定して撮影することが重要です。光量が十分でない場合は、フラッシュの使用も検討しましょう。ただし、フラッシュを使用する際は、お子様の目に直接光が当たらないよう注意が必要です。
手ブレに心配ならジンバル使用も一考

ジンバルという撮影アシスト機材をご存知でしょうか?
グリップの先についた「可動式部位」にスマフォをアタッチすることで、強力な手ブレ補正が可能となる器具です。
シャッターはグリップで操作できることから「シャッタータップによるブレ」をなくし、かつグリップのホールド力で固定された撮影ができます。
1万円以下で購入できるものも多数ありますので、使用を検討されてはいかがでしょうか。
3.画質設定はフルサイズで

スマートフォンの画面では美しく見える写真でも印刷となると必要な解像度が全く異なってきます。
画質設定は必ず高画質で
ここ3年に発売されたスマホであれば特段「解像度」を気にする必要はありませんが、Andoroidのように前もって「画質を下げる設定」がある場合、この操作は避けるべきです。
「画質を下げる=スマホ内の保存容量が増える」といった目的で、画質低設定をされる方がいますが、それによって印刷推奨解像度に至らぬ場合、元も子もありません。
印刷の美しさを保つには画面表示の約5倍の解像度が必要となります。そのため、撮影時の画質設定は特に重要なポイントとなります。
アプリを経由するとさらに画質低下に
各々の卒アル委員がスマホ撮影した写真を、一つのスマホに集約する方法として思い浮かぶのが「LINEアルバム」でしょう。
ですがこのLINEアルバムに画像をシェアした時点で、元画像の解像度は大幅に圧縮されるのをご存知でしょうか。
このことから、どうしてもLINEを使用したいのであれば「トーク」に「元の写真サイズ」をONにして送信する方法を選びましょう。
この他、コラージュアプリや画像補正アプリなども、加工の後に書き出し時点で圧縮がかかるものがあります。
事前に「何を使用したらどの程度画質が下がるか」をテストしておくべきでしょう。
印刷に適した画質設定
画質設定とは「写真をどの程度高精細に仕上げるか」を決めるものです。
一眼レフやコンパクトデジタルカメラは「L・M・S」などのレベル表示、Androidスマートフォンであれば「高・中・低」などで表示されてるのが一般的です。
Lや高での撮影A3サイズ程度に拡大表示しても、肉眼でみたそのままの情景が再現できます。
一方Sや低はSNSなどに投稿する「モニターだけで見る」ライトな画像に適しています。
高画質で撮影すれば、保存容量は減りますが、その分、より多彩な使い方が可能になります。
撮影時に特に注意したい点としては下記の通りです。
- 1.可能な限り最高画質で撮影
- 2.RAW形式が使える場合は積極的に活用
- 3.容量不足への事前対策を忘れずに
2のRAW形式とは「カメラセンサーが捉えた生の画像データ」のことを示し、撮影後「画像補正ソフトやアプリ」を使用して、明るさや色味を調整することを前提とした形式です。
詳しくは下記のブログ記事をご覧ください。
解像度の基礎知識
写真の解像度は印刷品質に直結します。
一般的な印刷では300dpi(1インチあたり300ドット)以上の解像度が必要とされます。
例えば、A4サイズで印刷する場合、約3000×2000ピクセル以上の解像度が望ましいとされています。
ここ3年間で販売されてるスマホであればこのサイズは余裕で超えていますので安心です。
スマートフォンやデジタルカメラの設定ではこのような印刷時の必要解像度を意識して設定を行いましょう。
画質と保存容量のバランス
高画質設定では1枚あたりのファイルサイズが大きくなるため、保存容量の管理が重要になってきます。
ただし、容量を節約するために画質を下げることは得策ではありません。
以下のような対策を講じることをお勧めします。
- 大容量のSDカードやストレージの準備
- 定期的なバックアップの実施
- 不要な写真の整理を習慣化
データ管理の重要性
高画質写真の管理には、慎重な取り扱いが必要です。
特に写真データの移動や共有の際は画質が劣化しないよう注意が必要です。
写真のバックアップは、SDカードやクラウドストレージなど、複数の場所に保存することをお勧めします。
特に重要な行事の写真はその日のうちにバックアップを取るようにしましょう。
また、写真を共有する際は、LINEやメールなどのSNSでは画質が自動的に圧縮されることがあるため、オリジナルの画質を維持できる方法を選択することが重要です。
4.重要な行事にはカメラマンを手配

プロのカメラマンと一般の方では、写真の仕上がりに明確な違いが表れます。
特に運動会や発表会といった重要、かつ「動きのある」行事では、プロのカメラマンに撮影を依頼することで、より思い出深い一枚を残すことができます。
また、カメラマンに撮影を任せることで、保護者の方も行事そのものに集中して楽しむことができます。
プロカメラマン活用のメリット
プロのカメラマンは、技術面での優位性はもちろん、園児たちの最高の表情を引き出すノウハウも持ち合わせています。
費用面での懸念もあるかもしれませんが得られるメリットは大きいものです。
- 安定した高品質な写真が確保できる
- 行事に集中して参加できる
- 客観的な視点での撮影が可能
- 照明や構図の専門的なテクニックを活用できる
カメラマンならではの技術力
プロのカメラマンは、光の扱い方から構図の取り方まで、長年の経験に基づいた確かな技術を持っています。
特に室内での撮影や、動きの速い場面での撮影など、一般的には難しいシーンでもしっかりと対応できます。
また、複数の園児が登場する集合写真なども、拡大しても細部までくっきりと認識でき、さらに全員の表情を活き活きと捉えることができます。
思い出を楽しむ余裕
カメラマンに撮影を任せることで、保護者の方は我が子の成長する姿を心ゆくまで見守ることができます。
カメラのファインダーを通してではなく自分の目で直接見ることを多くの幼稚園保育園が推奨しています。
拍手や歓声をよそに、撮影に夢中になるあまり、ファインダーやモニターばかりを覗いてる親の姿は、子供もみたくないかもしれません。
カメラマン選定のポイント
写真撮影を依頼する際は、以下のような点に注意して選定を行うことをお勧めします。
- スールフォト撮影の実績があること
- 事前の打ち合わせが可能であること
- 撮影データの受け渡し方法が明確であること
実際の依頼に際しては、園の行事予定に合わせて早めに予約を入れることが重要です。
特に卒園シーズンは混み合いやすいため余裕を持った予約が必要です。
また、当日の撮影ポイントや注意事項なども事前に確認しておくことで、より満足度の高い写真を残すことができます。
カメラマン派遣に関するブログ記事が2つございます。
5. スマホ撮影の注意点
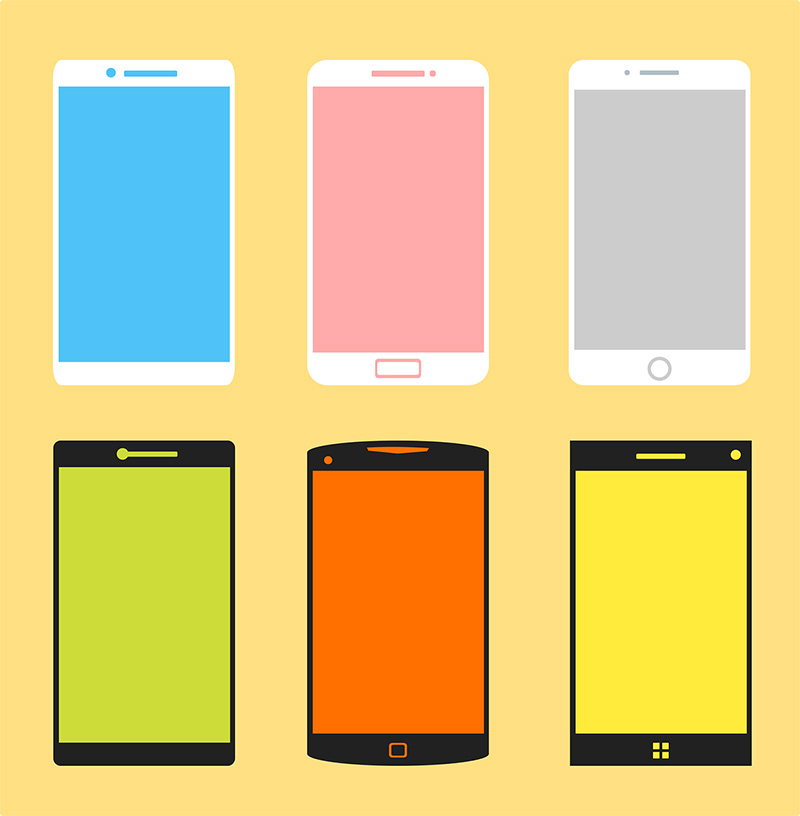
近年のスマートフォンは、高性能なカメラを搭載しており、適切に使用すれば一眼レフカメラに匹敵する美しい写真を撮影することができます。
しかし、その便利さゆえに陥りやすい落とし穴もあります。
卒園アルバムに使用する写真として最適な一枚を残すために、いくつかの重要なポイントを押さえておきましょう。
スマートフォンの特性を活かす
スマートフォンカメラの最大の魅力は、その手軽さと高い携帯性です。
しかし、便利な機能をやみくもに使用するのではなく以下のような基本的な注意点を意識することが重要です。
- デジタルズームは極力使用しない
- 逆光を避ける
- 手ブレ補正機能を活用する
- ポートレートモードを乱用しない
機種別の特徴と設定
Android端末は撮影前に画質設定を行うことができます。
必ず最高画質に設定し内部ストレージの空き容量も確認しておきましょう。
iPhoneの場合は、撮影時の画質設定はありませんが、写真を共有する際の画質設定に注意が必要です。
「画質:低」でシェアすると、高速転送が可能となり相手側のストレージに負担を与えないことから使用されがちですが、印刷推奨解像度を満たさなくなる可能性があります。
最適な撮影環境づくり
スマートフォンでも美しい写真を撮影するためには、適切な環境作りが重要です。
屋内での撮影時は十分な明るさを確保し、逆光は避けるようにしましょう。
また、指紋が付きがちなレンズの汚れもチェックする習慣をつけることでより鮮明な写真を撮影することができます。
こちらのブログも参考になさってください。
データ共有時の注意点
スマートフォンで撮影した写真を共有する際は、画質の劣化に特に注意が必要です。
LINEやメールでの送信時には、以下の点に気を配りましょう。
- 必ず高画質設定で送信
- LINEアルバムは使用しない
- Wi-Fi環境での送信を推奨
- オリジナルデータは必ず保管
特にiPhoneでは、写真を送信する際に画質を選択する画面が表示されます。
容量を節約したい気持ちは理解できますが印刷用の写真は必ず「元のサイズ」で送信するようにしましょう。
下の記事は写真転送の際の注意点をテーマに書いたものです。
おわりに
卒園アルバムの写真撮影には、日常のスナップ写真とは異なる配慮が必要です。
全身写真やアップ写真、画質設定、プロカメラマンの活用、そしてスマートフォン撮影時の注意点など、この記事でご紹介した5つのポイントを意識することで、より思い出深いアルバムを作ることができます。
お子様の大切な瞬間を、最高の形で残していただければ幸いです。撮影を楽しみながら、素敵な思い出作りをしていただければと思います。
今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それでは、また。

キッズドン! 代表 宗川 玲子(そうかわ れいこ)
(宣伝になります)
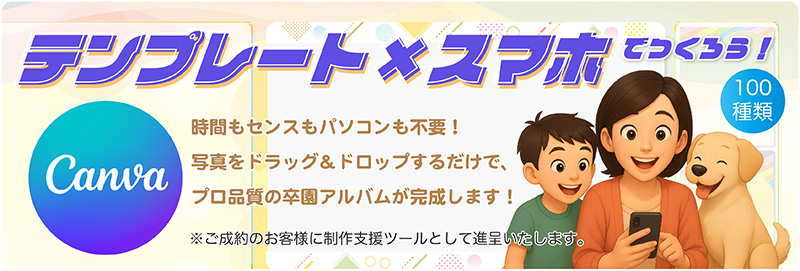
ご案内:キッズドン!の卒園アルバム制作方法の一つに、お客様ご自身で原稿制作を行う「そのまんまコース」があります。
このコースでご成約いただいたお客様へ「スマホだけで制作が完結するCanva専用100種類のテンプレート」を進呈しております。
リストにあるテンプレートをタップするとCanvaが起動し、すぐに作業をスタートさせることができます。
スマホ保存の写真をドラッグ&ドロップするだけで写真がテンプレートのフレームにフィットし、その場で画質補正やトリミングもできます。
シンプル操作のため、わずか20分程度(当社比)でプロ品質のアルバム原稿が完成!
詳しくはバナー、または下のボタンよりコンテンツに移動されご覧ください。
SNSで情報更新をお知らせします
ブログや、フリー素材の新作、ニュースなどの更新情報を、ツイッターとインスタグラムでお知らせしています。フォローしていただき最新情報をお受け取りください。










